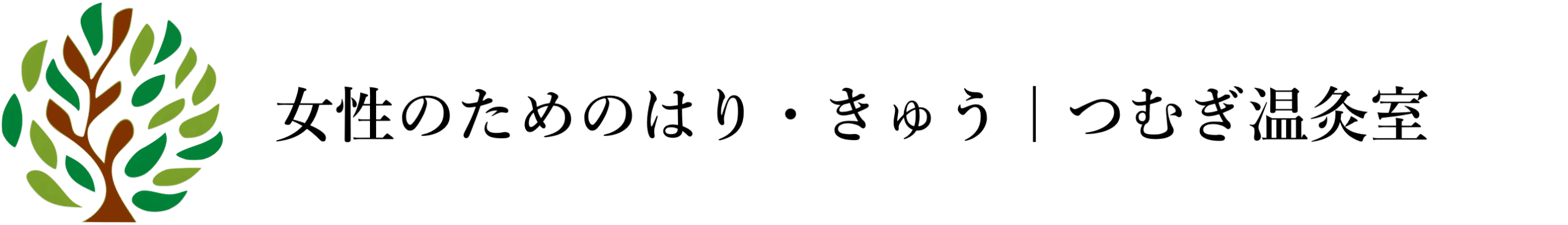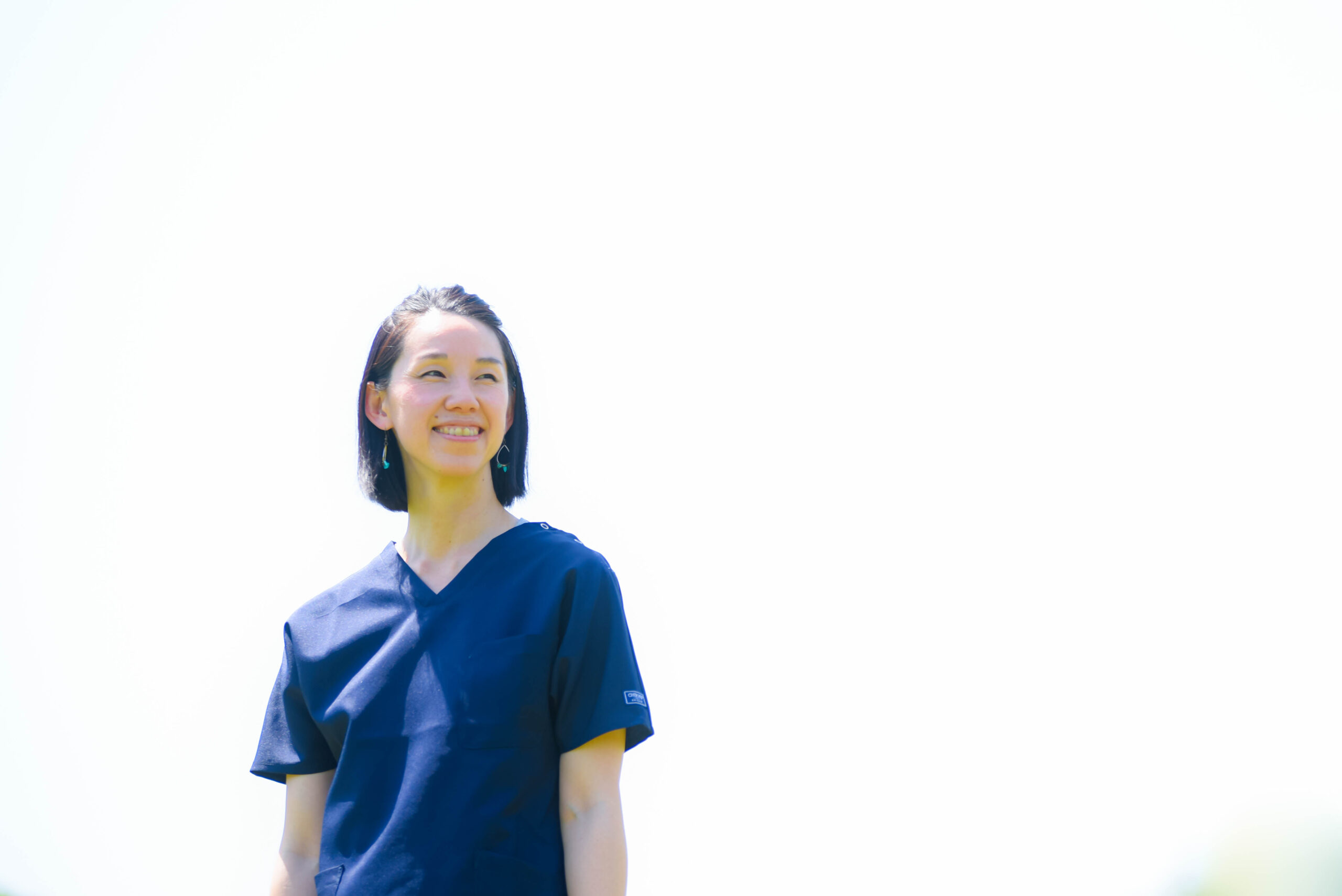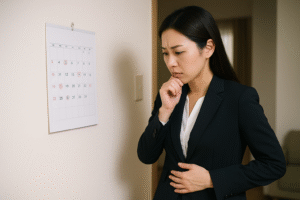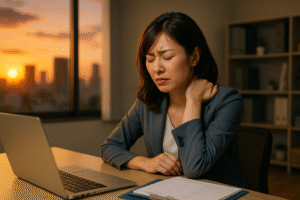【冷え・のぼせ】
鍼灸で整える身体の巡り
この記事でわかること
- 「下は冷え、上はほてる」の仕組み(自律神経・血流・ホルモン)
- 東洋医学の見立て(流れの渋滞/上熱下寒をやさしく解説)
- 見直すべき生活習慣
- 鍼灸で期待できること(足から温め、上の熱を静める)
- 今日からできるセルフケア
冷えなのに顔だけほてる——それは「上に熱・下が冷え」のサインです
手足は冷えるのに、顔や頭だけ熱っぽく汗ばむ……。
体の温度調整(自律神経)や血流のバランスが崩れると起こりやすくなります。
このページでは、なぜ起こるのか、鍼灸で期待できること、今日からのセルフケアをやさしくご案内します。
当てはまるものはありますか?(5つのチェック)

- 手足は冷たいのに、顔だけほてって赤くなる
- 夜になると頭が熱くて眠れない
- 冷房にあたると体は冷えるのに、首や顔から汗が出る
- 生理前後や更年期にほてり・汗が強まる
- 入浴後すぐ冷えて、温かさが続かない
なぜ「冷え・のぼせ」が生じるの?
自律神経と血流のアンバランス
自律神経は体温と血管の調整を担います。ストレスや睡眠不足などで自律神経が乱れると、末梢の血管が締まり下半身に血が届きにくく、逆に上半身には熱がこもりやすくなります。
さらに女性ホルモンの変化(生理前後・更年期)では血管の反応(収縮・拡張)が不安定になり、ほてり(ホットフラッシュ)や発汗が増えがちです。
長時間同じ姿勢や浅い呼吸、運動不足も冷えを助長し、のぼせとのアンバランスを招きます。
考えられる原因として

- 自律神経が乱れ、下半身は冷え、上半身がほてりやすい
- 首肩のこわばりと浅い呼吸で巡りが滞りやすい
- ホルモン変化で血管反応が不安定になりやすい
東洋医学では:流れの渋滞と「温める力・休む力」の不均衡
東洋医学では、からだを巡る「気・血」の流れと、温める力と冷ます力(陰陽)の釣り合いを重視します。
冷え・のぼせは「上は熱く、下は冷える(「上熱下寒」)」状態で、流れの渋滞により温かさや栄養が末端へ届きにくいのが特徴。
さらに「休んで回復する力」が弱いと、温めてもすぐ冷え戻るため、巡らせる・満たす・休むをバランスよく整えることが大切です。
こんな生活、続いていませんか?

- 冷暖房の効いた室内での長時間PC作業
- 入浴後、すぐに薄着や強い冷房に当たる
- 寝不足は、カフェインで補う
- 生理前後に予定を詰め込む
「
つむぎ温灸室のケアとセルフケア
-施術で整え、自宅で保つ——今日からの小さなコツ-
鍼灸で“足から温めて、上のほてりを落ち着かせる”
つむぎ温灸室では、やさしい鍼、温かいお灸で下半身を温め、全身の巡りを整える施術を行います。
足先までしっかりと温かさを届けつつ、上にこもった熱を落ち着かせます。
さらにカラダをしっかりと休むことができる方向に働きかけます。
体質や生活リズムに合わせ、無理のないペースで整えていきます。
改善ポイント

- 足先まで温かさを届け、冷え戻りを減らす
- 上半身のほてり・発汗を落ち着かせる
- 首肩のこわばりをゆるめ、呼吸を深くする
- 自律神経のバランスを整え、入眠を助ける
- 日中のだるさを軽減し、体力の回復を促す
今日からできるセルフケア
- 足首やふくらはぎを、レッグウォーマーなどで温めましょう。
- 深呼吸を習慣にしましょう。 副交感神経が整いやすくなります。
- ウォーキングや下半身を意識した軽いスクワットをやってみましょう。
- 入浴は「ぬるめ(38~40℃)のお湯でゆっくり(10~15分)」がおすすめ
- 趣味や自然に触れる時間を作り、ストレスをため込まないようにしましょう。
足元から温めて、上の熱を静める時間を
冷え・のぼせは、からだの「流れ」と「温める力・休む力」のバランスが崩れて起こりやすくなります。
足元からやさしく温め、上の熱を落ち着かせることで、少しずつ楽になる道筋があります。
つむぎ温灸室では、一人ひとりの体質に合わせた施術で、
心身をやさしく整えていきます。
「手足は冷えるのに、顔だけほてる」
「夜に頭が熱く、寝つきにくい」
「入浴後すぐ冷え戻り、温かさが続かない」
そんな方は、どうぞお気軽にご相談ください