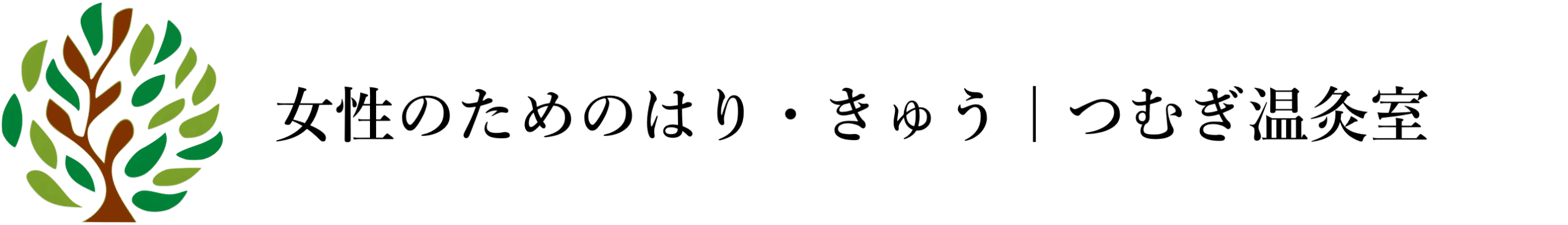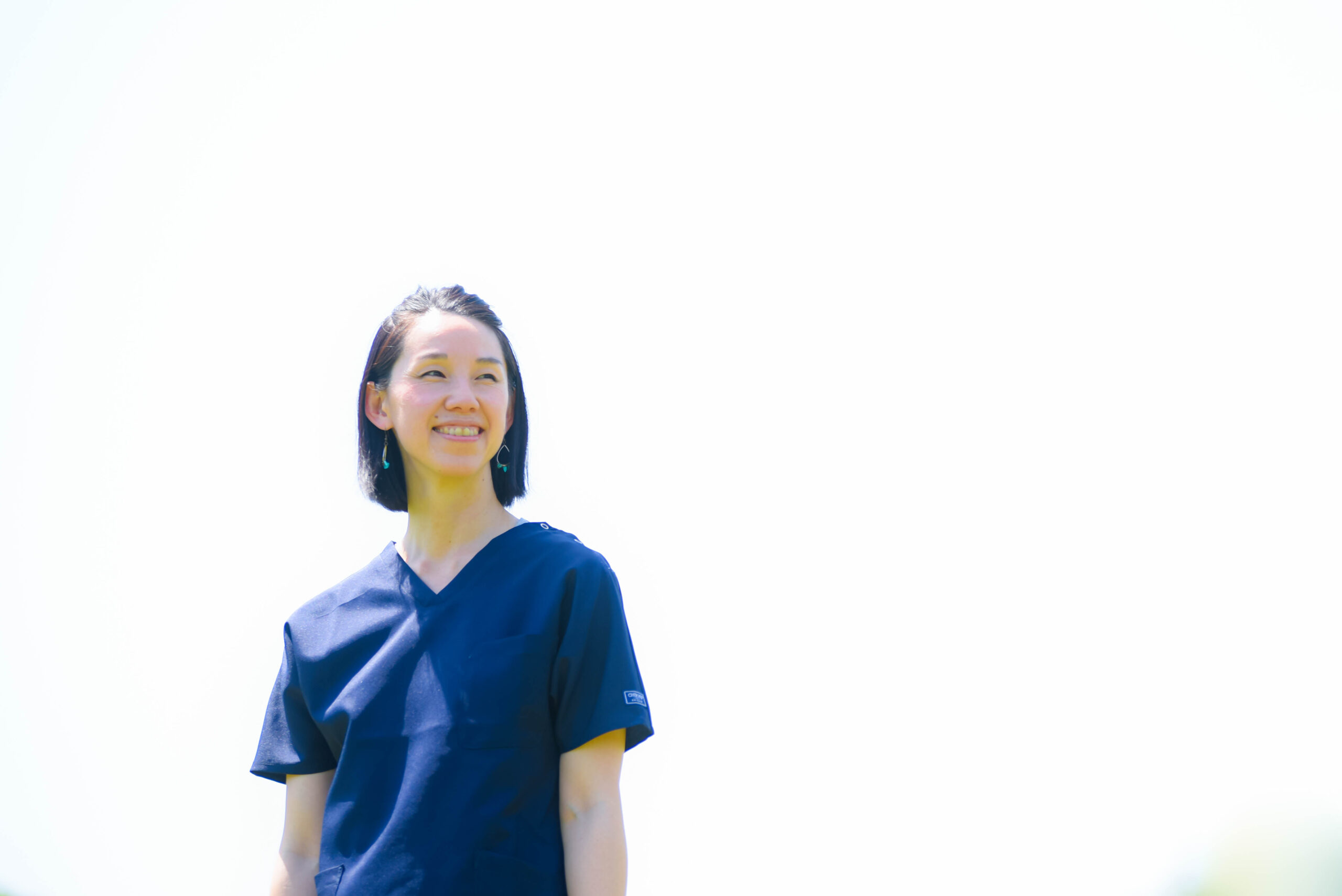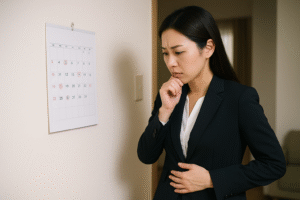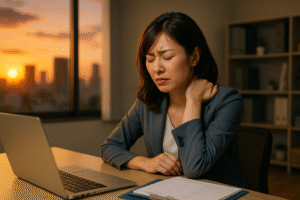【更年期の不調】
鍼灸で整える揺らぎの時期
この記事でわかること
- 更年期の不調のしくみ(ホルモン・自律神経)
- 東洋医学の見立て(流れ・陰陽の揺らぎ)
- 見直すべき生活習慣
- 鍼灸で期待できること(ほてり・睡眠・気分)
- 今日からできるセルフケア
急なほてり・汗が続く——それは「女性ホルモンのゆらぎ」です。
45〜55歳ごろに多い、体と心のゆらぎ。
女性ホルモンの変化に自律神経が引っ張られ、ほてり・発汗・睡眠の乱れ・気分の波が出やすくなります。
このページでは、理由と整え方、鍼灸で期待できること、今日からのセルフケアをご案内します。
当てはまるものはありますか?(5つのチェック)

- 突然のほてり・汗(ホットフラッシュ)が気になる
- 夜中に汗で目が覚め、眠りが浅い
- 動悸や不安感を感じる
- 肩こりや関節のこわばり・だるさが続く
- 気分の波・イライラ・落ち込みが増えた
なぜ「更年期の不調」が生じるの?
ホルモン変化に体温調節と睡眠がゆさぶられる
女性ホルモン(卵巣ホルモン:エストロゲン)の低下により、体温調節や血管の反応が不安定になり、ほてり・発汗が起こりやすくなります。
同時に自律神経と睡眠のリズムも影響を受け、入眠しづらい・途中で目が覚めるなどの睡眠の乱れ、気分の波やだるさが重なりやすくなります。
冷え・運動不足・ストレスは血流を落とし、症状を長引かせる要因になります。
考えられる原因として

- 卵巣ホルモンの変動で体温調節が不安定に
- 交感神経優位と睡眠不足の連鎖
- 冷え・運動不足・ストレスで血流低下
東洋医学での見立て:流れの渋滞と「上の熱・下の冷え」「潤い不足」
からだを巡る「気・血」の流れが渋滞すると、上には熱がこもり(ほてり・汗)、下は冷えやすくなります。
さらに「潤いを養う力」が弱ると、のぼせ・乾燥・不眠が出やすい傾向に。
巡らせて、温めて、養う——この3つの土台を整えることが大切です。
こんな生活、続いていませんか?
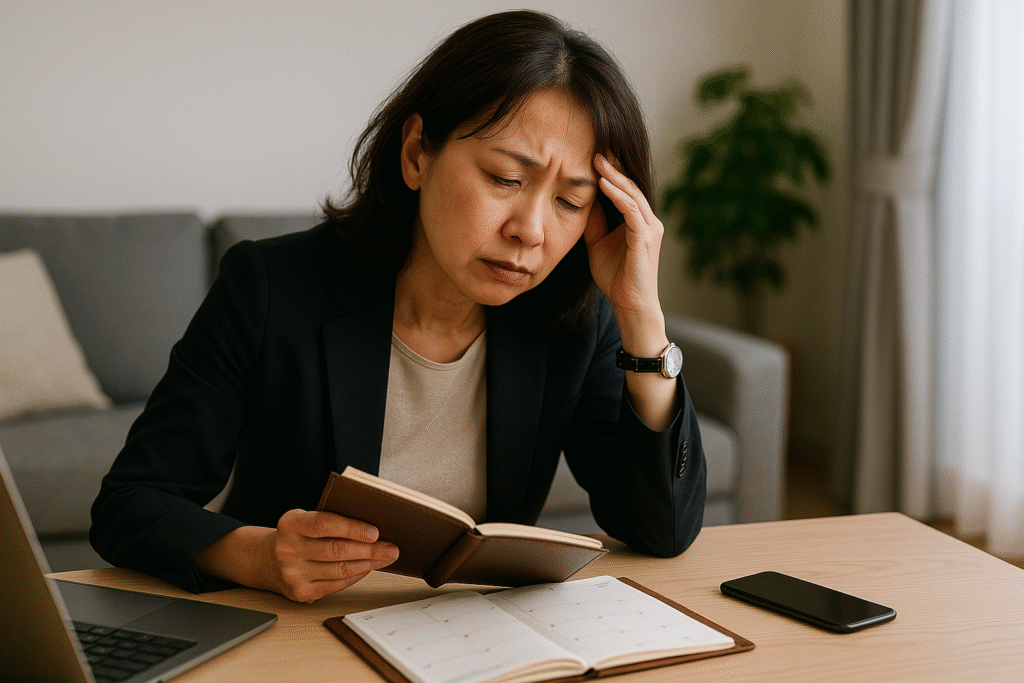
- 辛い料理・熱い飲み物・アルコールでほてりが増幅
- 就寝直前までスマホ・パソコンを使用
- 冷暖房の出入りが多く、体温差ストレスが大きい
- 予定を詰め込み、休む時間が作れない
つむぎ温灸室のケアとセルフケア
-施術で整え、自宅で保つ——今日からの小さなコツ-
鍼灸で“上のほてりをしずめ、巡りと眠りを整える”
胸・首肩・背中・お腹・骨盤まわり・足首を中心に、やさしい鍼と温かいお灸でじんわり緩めます。
足元から温かさを通し、上にこもった熱を落ち着かせ、呼吸と睡眠のリズムを整える後押しをします。
体質や生活に合わせ、無理のないペースで整えていきます。
改善ポイント

- ほてり・発汗の頻度と強さの軽減
- 入眠しやすく、夜中の目覚めが少なくなる
- 首肩・関節のこわばり、頭重感の緩和
- 不安感・イライラが抑えられ、気分の波が安定
- 足元の冷えが改善し、体温調節がしやすく
今日からできるセルフケア
- 深呼吸「4-6呼吸」:4秒吸って6秒吐くを1〜3分、1日2〜3回
- 寝室はやや涼しめ・通気よく。重ね着で体温調整しやすく
- 辛味・アルコール・熱い飲み物は控えめに
- 朝の外歩き10〜15分で日光を浴び、体内時計を整える
- 入浴は38〜40℃で10〜15分。上がったら足元を保温
揺らぎに寄りそう、やさしい時間を
更年期の不調は、からだの「流れ」と「休む力・養う力」のバランスが揺らいだサインかもしれません。
足元から温め、上の熱を落ち着かせ、呼吸と眠りを整えるところから、少しずつ楽になる道筋があります。
つむぎ温灸室では、一人ひとりの体質に合わせた施術で、
心身をやさしく整えていきます。
「突然のほてり・汗がつらい」
「眠りが浅く、だるさが抜けない」
「気分の波や不安感が気になる」
そんな方は、どうぞお気軽にご相談ください